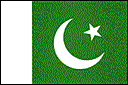
◆◆◆ 我がハザラ族・我がキッコ−マン ◆◆◆
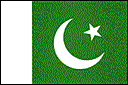
「昔、我々は一つだった」と年老いたムジャヒディンに話かけられたことがある。
ムジャヒディンは、みんなムジャムジャと髭を生やしていて、でも、それはあんまり関係ないらしくて、ムジャヒディンとは「聖戦士」というような意味らしい。
要する に1978年にアフガニスタンにソ連が進攻して傀儡政権を立てて以来、政府軍相手に戦い続けているアフガンゲリラのことである。
アフガンゲリラはイスラムの大義を守るために「聖戦」を戦っているので「聖戦士」なのだ。
もうソ連軍は撤退したし、去年の4月に共産党政権も倒れたので、聖戦士は必要なくなったはずなのだけど、今度は
戦後復興の主導権をめぐって、何十もあるムジャヒディンの派閥が壮絶な戦闘を始めてしまい、収拾がつかなくなった。
もはや、誰が誰と何のために殺し合いをしているのか分からなくなり、その間に首都を含めほとんどの都市は破壊されてしまった。
不幸な話ではないか。
よそ者が気まぐれにちょっかいを出したばっかりに同国人どうしの争いで一国がむちゃくちゃになってしまったのだ。
かつてアフガニスタンの首都カブール はアジアのパリと呼ばれていたくらい美しい街だったそうだけど、今はただ の瓦礫と死体の山。
このムジャヒディン同志の抗争が去年の8月に起きなければ、僕はカブールに赴任の予定だった。無念じゃ。
ところで、このムジャヒディンの老人は日本人そっくりの顔をしている。
彼はかつてチンギス・カンがモンゴル帝国を築き、その息子や孫達が帝国をインド、中央アジアそしてヨ−ロッパまで拡張していった時に、アフガニスタンまでやってきたモンゴル騎馬戦士の子孫なのだ。
そして、数百年を経て、先祖と同じように、剣をアメリカ製マシンガンに持ちかえ、今また戦っている。
彼は僕を生粋のモンゴル人だと思ったのだろうか。
それとも、自分の先祖と同じようにかつてモンゴル帝国が世界を支配していた時に自分の先祖とは反対にどこか東の方へ行ったモンゴル人の子孫だと思っていたのだろうか。
それとも、僕をイトコのオジイサンの弟のオバサンのマタイトコの孫の末っ子の嫁のハトコの甥っ子みたいな遠い親戚だと思ったのだろうか。
言葉が通じないので詳細は分からない。
いっしょにいた若いムジャヒディンもほんの少ししか英語を知らない。
−−昔は一つだったと云 っている−−。
彼が通訳できたのはそれだけだった。
老人は長い間僕の顔を静かな目でじっと見ていた。
僕の顔を見るというより、僕の顔を通り越してどこかずっと遠くを見ているようだった。
過ぎ去った長い時間を見ていたのだろうか。
遠い地平線の果ての未だ見ぬ先祖の国を思い描いていたのだろうか。
それとも目が悪かったのだろうか。
もう戦いをやめればいいのに。
ほんとにそう思った。
このモンゴル帝国人の子孫は今ハザラ族と呼ばれている。
俗称、チンギ−シ−。 チンギス・カンのチンギスの派生語だ。
「我々が戦っているのに、お前ら日本人は助けに来なかった。
恥ずかしいことだぜ 、まったく、ああ恥ずかしい」とケ−キ屋のにいちゃんに言われた。
笑っていたけど 、少し本気なのかもしれない。
彼もハザラ族だ。
彼の論理によると、日本人もハザラ族の一員なのだから、アフガニスタンのハザラ族がル−シ−(ロシア人)と戦っているときは日本人も協力してル−シ−相手に戦うべきなのだ。
「日本人は忙しいのだ」ととりあえず言っておいた。
彼は10代後半か20代前半だろう。
ちゃんとした英語を喋る。
きっと彼が幼児の頃、両親と共にパキスタンに逃げてきたのだろう。
今はイ スラマバ−ドで一番繁盛しているケ−キ屋をきりまわしている。
パスポ−トもヴィザも労働許可もへったくれも無いのはみんな知っている。
それでも、ここのクッキ−は 、伝統的なパキスタンのお菓子と違って、甘さひかえめで、とてもおいしいから、法律なんかどうでもいいのだ。
クッキ−をつまみ食いしながら、へらへらとそんな同胞論議をしていたある時、彼が背にする棚でひっそりと美しくも、まばゆい光を放つ、可憐な黒いボトルを僕の目はしかと認知した。
ショ−ユだ。
醤油である。
あのしょうゆである。
それもキッコ−マンという豪華絢爛上等舶来ブランドものである。
「エライ!君は天才だ。
そうだ、日本人は皆悪い。
卑怯者だ。臆病者だ。しかるに君は正しい。
君は美しい。
ワンダフルだ!」と、僕は正当にも全ての日本人を微塵も躊躇せず 一瞬で裏切り、彼の商品仕入センスを絶賛しまくって、棚にあるキッコ−マンを断固すべて買い取った(といっても4本しかなかったけど)。
−推論−
僕の今の仕事で最も大事なことの一つに、緻密な推論をする、ということがある。
いろんな証言、証拠、資料、法律などを組合せて、法的推論を構成して結論を出す。
この結論を出すまでの作業自体が難しくて、しかも大量のケ−スを短時間に処理して次々に説得力のある報告書にまとめて本部に送り続けなければいけないので、知的にも肉体的にも重労働なのだけど、それ以上に負担なのはこの結論に一人一人の人生
が、生命が、かかっているということである。
リ−ガルセクションのオフィサ−には 、この精神的負担に押しつぶされずに緻密な推論を毎日ヘラヘラ笑って正確にこなしていく、健康で強靭な精神力、もしくはまったくの鈍感で無神経な愚鈍さを要求される。
しかし、残念なことに、最近こういう点で深く反省すべき出来事が起った。
パキスタンに来て間もない頃、道端で世間に背を向けてしゃがんでいるパキスタン男がいるのに気が付いた。
しゃがんで何をしているのだろう、うつむいてみんなに背を向けて、何か嫌なことでもあったのだろうか、誰かに怒られて見せしめにすねているのだろうか、なんて考え始めると気になってちょっと挨拶しに行ってみたくなったけど、明らかに彼の背中のまるめ方は「一人にしておいてくれ」と言っていたので
、邪魔しないことにした。
しかし、それから、よく注意してみると、あちこちにしゃがみ男がいるのに気が付き始めた。
みんな、もぞもぞしてる。
みんなうつむいている。
そうか、みんなウンコしてるんだ。
なるほどねえ、パキスタンには公衆便所ないもんな、フムフム。
と、迂闊にも納得して1ヵ月も経ったある日、アッ! 水がない!ということに気が付いた。
水がないとパキスタン人はウンコできないではないか。
彼らがしていたのはウンコではなかったのだ。
まったく迂闊であった。
愚鈍さの極致である。
彼らは 皆、道端ですわってオシッコしていたのだ。
(1)文化的偏見−男はオシッコを立ってするものだ−及び、
(2)事実の見落とし−水がない−という二重の初歩的ミスによって、恐ろしく誤った結論を出していたのだ。
教訓
(1)まだまだ文化的偏見が性根から払拭できていない。
(2)事実把握がまだまだ甘い。
(3)パキスタンの男はすわってオシッコする。