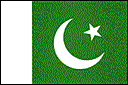
◆◆◆ 千夜一夜なんやかんや物語 ◆◆◆
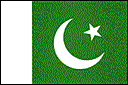
『アリババと41人の盗賊(40人だったかな?)』に登場する洞窟、あの「開けえ、ゴマ!」で開く洞窟が、クエッタにあるのだ。
盗賊も少し増えて、推定41000 人くらいいる。
イギリス人のバカが植民地時代にこの洞窟をトンネルにして線路を敷いてしまったけど、今は汽車を通さず、史的記念物として保存されているらしい。
僕はまだ見に行ってないけど、絶対見に行こうと思っている。
しかし、驚きだ。
千夜一夜物語というのは、もちろん作り話だけど、それぞれの 話はまったく荒唐無稽というわけではなくて、登場する街や人物はみんなモデルがあり、それぞれ今でも確認できるという。
この辺の子供はみんな千夜一夜物語を聞かされて大きくなるそうだ。
地域によって少しずつ、ヴァリエ−ションがあるのは日本の民話と同じ。
毎朝僕の部屋でやるミ−ティングで、ある時『シンドバッドの冒険』の話をしてくれと言ったら、通訳のモハメッド・アリ(パキスタン人)と助手兼秘書の
ルストム・アマリア(イラン人)が話の筋で抗争を始めてしまった。
僕があわてて「物語というのは生き物だ!」と言ったので、二人は怪訝な顔をして抗争は停戦状態に入った。
この千夜一夜物語の作者は、南アジア、中央アジア、西アジア一帯を旅して、各地でいろんな題材を拾って、それを物語にして残したらしい。
そのうち、時間を作って、千夜一夜物語を手に入れて読み始めよう。
この街はほんとに飽きない街だ。
興味が尽きない。
中学校や高校で習った歴史が そのまま目で見て手で触れる。
僕は時々仕事の帰りに骨董品屋に寄る。
骨董品屋の主 人はどういうわけか、たいていアフガニスタン人で、鋭く用心深い目付きで、警戒心まるだしの応対をしてくれる。
やれやれ、サ−ビス産業のイロハを知らないのかと言いたくなるけど、もう慣れてしまったので、陽気に「ハロ−!」と言って手を差し出すと、向こうも手を出し握手をして警戒心を解除する。
すると僕はもう彼らの客人になってしまい、上へ下へのもてなしということになる。
お腹がだぶだぶになるまでグリ−ンティ−を飲まされ、延々2時間くらいは商談に花が咲く。
グリ−ンティ−というのは、アフガニスタン名物で、彼らはこれに大スプ−ンに山盛り2杯くらいの砂糖を入れて飲む。
味は日本の普通のお茶と同じなので、僕は砂糖なしで飲みたいのだけど、彼らにとって砂糖山盛りは最高のもてなしなので、どうしても断り切れない。
この味も、もう慣れてしまった。
彼らはたいてい美しい石の指輪とかピアスとかネックレス、あるいは絨毯なんかを薦めるのだけど、僕が興味のあるのはそういうものでなくて、店のすみっこに転がっている汚い石の人形とか鉄屑みたいな物体なのだ。
ひょっとしたら、こういうガラクタの中に歴史的に非常に重要なものがあるかもしれないと思って、僕は一つずつ丹念に検証していく。
オッ、これはメソポタミア文明くさい!とか、オッ、これはモヘンジョ・ダロ関係かも知れん、なんて一人で楽しみながら。
しかし、店の主人や店員らはそんなものにてんで関心がないらしい。
ほんとにただのゴミだと思っているみたいでごみ箱みたいな箱にどさっとまとめて突っ込んでいたりする。
いったい、どこか らこういうものを仕入れてくるのだ、ときくと、「ムジャヒディン持ってくる、地面掘る、いっぱいある、戦う、休む、地面掘る、ムジャヒディン、ドル要る、武器買う、これ古い、古い」。
なるほどねえ、ムジャヒディンの副業か。
いったん、僕がこういうものに興味があるのだ知ると、彼らは次から次にどこかにしまいこんでいたガラクタをひっぱりだしてきて、ほんの数秒前までゴミだと思っていたくせに、急にもったいつけて、これは500年くらい前のものだとか、これは1400年くらい前のものだとか適当なことを言って商売を始める。
彼らはまったく何にも分かっていないふしがあって、明らかにごく最近のブリキのおもちゃだと思われるようなものまでいっしょくたにして古代文明の仲間に入れてしまう。
もちろん、僕は何にも言わないけど、彼らの調子の良さには笑ってしまう。
というわけで、時々僕はこうやって古代文明から現代までのゴミの歴史を楽しむ。
もっと専門知識があれば、本当にゴミの鑑定がちゃんとできて、おもしろいだろうなあとつくづく思う。
そういうことを研究している人にとっては、僕は贅沢な、妬ましい境遇にいることになるんだろうけど、残念ながら僕は考古学の知識ゼロである。
なんとももったいない、猫に小判・豚に真珠的状況である。
知識人は不可避的に孤独になるけれど、物理的孤独から人間を救ってくれるのは、知性と教養だというのに! ・・・・・・?
国連職員の多くは、まったく地元コミュニティと交わろうとせず、関心も示さない。
もちろん、例外もあるけれど。
何年いても地元の言語をまったく覚えようとしない。
外国人どうし集まっては、パ−ティ−をし、酒を飲み、ぐちを言っている。
待遇が悪い(これ以上いったい何を求めるのか僕にはさっぱり理解できない)とか、退屈だとか、この国は最低だとか、なかなか昇進のチャンスがないとか、まったく欝屈している人にたくさん出会う。
イスラマバ−ドには国連クラブという超植民地主義的なクラブがある。
その中には、芝生の庭にプ−ルがあり、バ−があり、いつでも世界中の酒がドルで飲めるし、おそらくパキスタン全土で最高の西洋料理が食べれる。
厳格な会員制で、国連職員は50ドル、外交官は500ドル払えば会員になれるが、現地人は絶対に会員になれない。
要するにここはパキスタンではない。
昔の上海なんかにあった租界地のクラブってこんな感じだったのだろうか。
ここにアル中の国連職員がたむろしている。
虚ろな目をして世をはかなみながら、同情の声がかかるのを毎夜待っている。
これが植民地根性のなれの果てなのだ。
こういう精薄関係者が作り出す自家製の不幸に付き合うことほど不愉快なものはない。
周りにいちいち報告せずに勝手 にどん底に転がり落ちればいいのに、こういう輩に限って、いつまでも一緒に墜ちていく連れ合いを求めるのでたちが悪い。
うしろからポンと押してやりたい衝動に駆られる(この点、ヴァン・ヘイレンはエライ。飛び下り自殺志願者に、跳べ、跳べ、と
けしかける歌を全世界でヒットさせてしまったのだから)。
もう彼らの人生は終わっているのだから、物理的な死とか生は既に意味がない。
どっちでも同じことだ。
余談だけど、観念的な死に取りつかれた人は、クセジュ文庫の『死』という本を読むことを薦める。
生命体にとって死とは何かを徹底的に解明していて、そのあまりの即物的な叙述に、情緒的な死の観念はぶっとんでしまうことを保証する。
僕は最後に笑ってしまった。
もう15年くらい前の話だけど。
しかし、すべての国連職員、外交官がこんなにつまらない人間ばっかりなわけではない。
あるパ−ティ−で定年まじかの国連職員にあった。
彼はカナダ人で元々軍人だったけど、足を負傷して1本不自由になってから、国連に入った。
今、僕の所属す るUNHCRを含め、いろんな機関を渡りあるき、今はパキスタンのUNDPで一番エライ人である。
奥さんは日本人でニュ−ヨ−クでデザイナ−としてバリバリと活躍しているらしい。
一年に何回かニュ−ヨ−ク、東京、イスラマバ−ドのどこかで会うといっていた。
彼はパ−ティ−に来ている外交団や国連関係者の深刻ぶった話が好きじゃないらしくて、時々そんな会話をちゃかす一言を入れては、一人でガハハハと大声で笑っていた。
おもろいオッサンやなあと思って、しばらく話をしてみて、すごくホッした。
一つには、久しぶりの美しく分かりやすい英語に、もう一つには彼の話そのものに。
彼はいかにパキスタンという国が興味深い所であるかを僕に教えようとしていた。
そして外国人の多くがいつも固まって、地元のおもしろさに気がつかないことを嘆いていた。
彼はあと5年頑張って、この地で定年を迎えるのだ、ガハハハと笑っていた。
アフリカの様々な国を渡り歩いたこと、ニュ−ヨ−クやジュネ−ヴに赴任した頃のことなど、いろいろ語ってくれた。
「いろんなことがあった。世界中を経巡った。危険もいっぱいあった。
決して楽な仕事じゃない。
しかし、大事なことを一つ 教えてやろう。
それは、もし、わしが億万長者に生まれていたとしたら、ちょうど今とまったく同じ人生を送っていただろうということだ。
それをわしはお金をもらって送ったのだ。ガッハッハッハッハ。
違いは、億万長者は自分のお金をつかう。
わしは 他人のお金をつかうってことだ。
愉快じゃないか、ガッハッハッガッハッハッハッハッハッハ。
そうだ、明日インスタント味噌汁を君にあげよう。ガッハッハッハ」。
あれから、僕の部屋に回ってくる文書に時々、彼のサインを発見してはガッハッハを思いだして、愉快になってしまう。
あのオッサンは現代のシンドバッドかもしれない。